デイケア(通所リハビリテーション)で算定できる加算とは?単位や算定要件について解説
2025年10月15日

通所リハビリテーションは、通所施設(病院、診療所、介護老人保健施設など)に通う利用者に対して、リハビリによって身体機能の維持・向上や、社会参加を支援するサービスです。本記事では通所リハビリテーションの加算項目について算定要件や単位について解説します。
通所リハビリテーションとは
通所リハビリテーションとは、要介護認定を受けた高齢者が自宅での生活を維持できるよう支援するサービスです。介護老人保健施設や病院、診療所などに通い、食事や入浴のサポート、機能訓練、口腔機能向上サービスを受けられます。
要介護認定を受けた方を対象とし、介護予防や生活機能の維持を目的としています。利用者負担は事業所の規模や利用時間、要介護度によって異なります。
通所リハビリテーション加算項目一覧
通所リハビリテーションでは、さまざまな加算・減算項目が設定されており、利用者の状態やサービスの提供内容に応じて適用されます。
・利用者の数が利用定員を超える場合又は医師、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合
・高齢者虐待防止措置未実施減算
・業務継続計画未策定減算
・感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合
・理学療法士等体制強化加算
・7時間以上8時間未満の通所リハビリテーションの前後に日常生活上の世話を行う場合
・リハビリテーション提供体制加算
・中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
・入浴介助加算
・リハビリテーションマネジメント加算
・短期集中個別リハビリテーション実施加算
・認知症短期集中リハビリテーション実施加算
・生活行為向上リハビリテーション実施加算
・若年性認知症利用者受入加算
・栄養アセスメント加算
・栄養改善加算
・口腔・栄養スクリーニング加算
・口腔機能向上加算
・重度療養管理加算
・中重度者ケア体制加算
・科学的介護推進体制加算(LIFE加算)
・事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所リハビリテーションを行う場合
・送迎を行わない場合の減算について
・退院時共同指導加算
・移行支援加算
・サービス提供体制強化加算
・介護職員等処遇改善加算
なお、利用者が以下のサービスのいずれかを受けている日は通所リハビリテーション費を請求できません。
・ 短期入所生活介護
・ 短期入所療養介護
・ 特定施設入居者生活介護
・ 小規模多機能型居宅介護
・ 認知症対応型共同生活介護
・ 地域密着型特定施設入居者生活介護
・ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・ 複合型サービス
通所リハビリテーション加算・減算項目の種類
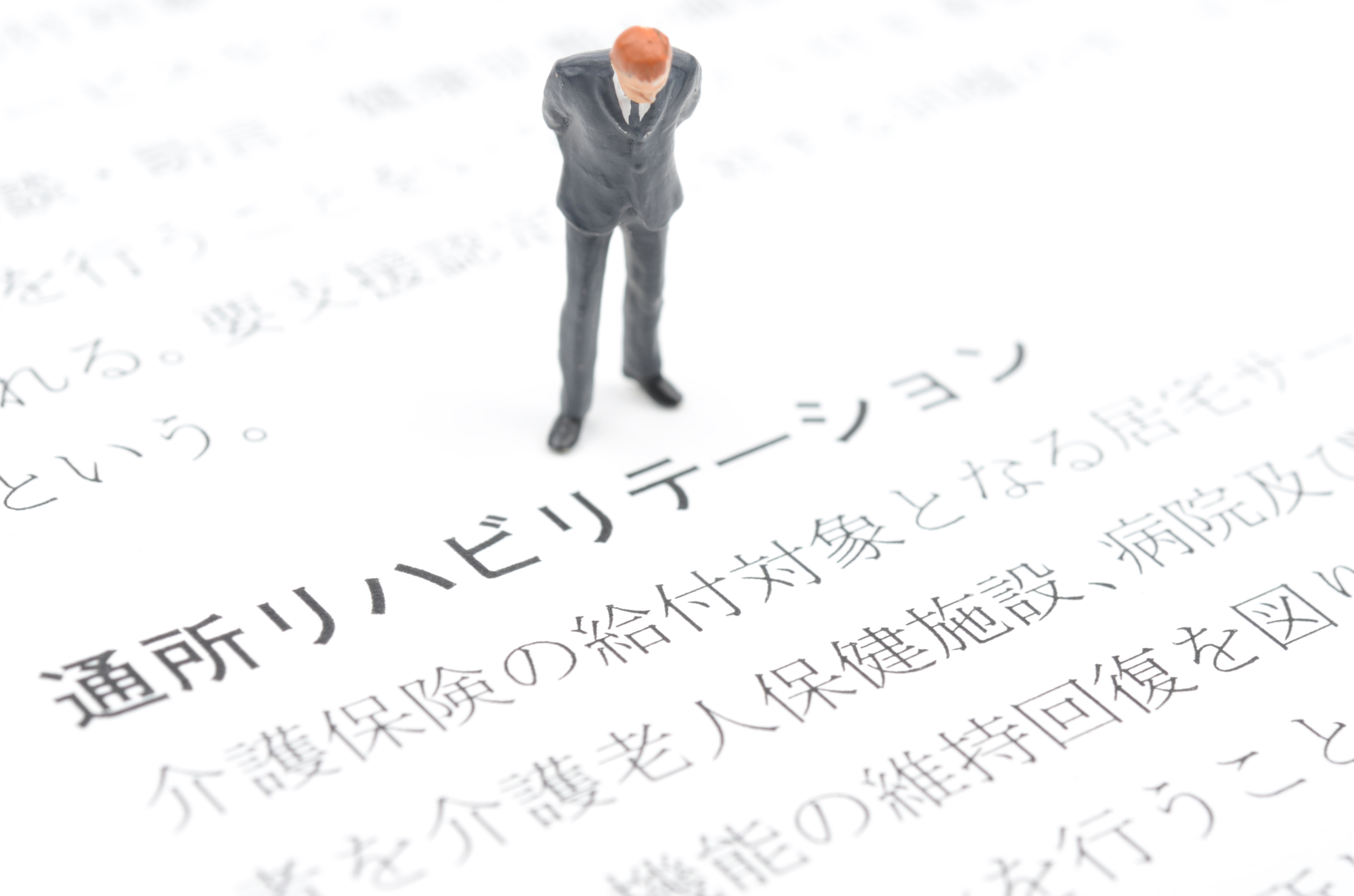
通所リハビリテーションでは、利用者の状態や提供するサービス内容に応じたさまざまな加算・減算が設けられており、適切なケアの提供を促進します。
以下に、主な加算・減算項目を紹介します。
利用者の数が利用定員を超える場合又は医師、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合
定員超過時または人員基準を満たさない場合は30%の減算です。
項目一覧に戻る高齢者虐待防止措置未実施減算
事業所が高齢者虐待防止措置を適切に実施していない場合、所定単位数の1%の単位数が減算されます。
項目一覧に戻る業務継続計画未策定減算
感染症や災害発生時の業務継続計画が未策定の場合、所定単位数の1%が減算されます。
項目一覧に戻る感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合
感染症や災害により利用者数が前年度平均より5%以上減少した場合、都道府県知事へ届出を行うことで、所定単位数の3%が加算されます。
利用者数が減少した月の翌々月から3か月以内に限り算定可能です。ただし、利用者数の減少に対応するための経営改善に時間を要すること、その他の特別の事情があると認められる場合は、期間が終了した月の翌月から3か月以内に限り、引き続き加算を算定することができます。
項目一覧に戻る理学療法士等体制強化加算
専従かつ常勤で2名以上の理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士を配置し、1時間以上2時間未満の基本報酬を算定していることが要件となります。加算単位数は1日あたり30単位です。
項目一覧に戻る7時間以上8時間未満の通所リハビリテーションの前後に日常生活上の世話を行う場合
通所リハビリテーションの合計時間が8時間以上となった場合に適用される加算です。対応時間ごとの加算単位数は以下のとおりです。
| 項目 | 加算単位数 |
|---|---|
| 8時間以上9時間未満 | 50単位 |
| 9時間以上10時間未満 | 100単位 |
| 10時間以上11時間未満 | 150単位 |
| 11時間以上12時間未満 | 200単位 |
| 12時間以上13時間未満 | 250単位 |
| 13時間以上14時間未満 | 300単位 |
項目一覧に戻る
リハビリテーション提供体制加算
リハビリテーション提供体制加算は、通所リハビリテーション事業所が適切なリハビリ提供体制を確保していることを評価する加算です。常に、事業所にいる理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の合計が、利用者25人ごとに1人以上配置されている必要があります。
| 所要時間 | 加算単位数 |
|---|---|
| 3時間以上4時間未満 | 12単位 |
| 4時間以上5時間未満 | 16単位 |
| 5時間以上6時間未満 | 20単位 |
| 6時間以上7時間未満 | 24単位 |
| 7時間以上 | 28単位 |
項目一覧に戻る
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
厚生労働大臣が定める中山間地域等に居住する利用者へ、通常の事業実施地域を超えて通所リハビリテーションを提供する事業所に適用されます。加算単位数は所定単位数の5%で1日につき加算されます。
留意点
● この加算を適用する利用者については、交通費の別途請求は不可
● 中山間地域には、離島・豪雪地帯・辺地・山村・過疎地域などが含まれる
入浴介助加算
入浴介助加算は、利用者が安全かつ自立的に入浴できるようにつくられた加算です。
| 項目 | 加算単位数 |
|---|---|
| 入浴介助加算(Ⅰ) | 40単位/日 |
| 入浴介助加算(Ⅱ) | 60単位/日 |
項目一覧に戻る
リハビリテーションマネジメント加算
リハビリテーションマネジメント加算は、医師とリハビリ職が中心となって多職種でリハビリテーションの質を管理するために都度方針を見直す体制を整えた事業所が算定できる月額加算です。個別リハビリ計画を作成し、1か月または3か月ごとに評価や会議を行います。利用者への説明・同意や、LIFEを活用したデータ提出・活用なども要件に含まれます。重度化防止やADL向上を目的に、継続的なPDCAサイクルを重視した加算です。
| 項目 | 加算単位 |
|---|---|
| リハビリテーションマネジメント加算(イ) | (1)6か月以内:560単位/月 (2)6か月超 :240単位/月 |
| リハビリテーションマネジメント加算(ロ) | (1)6か月以内:593単位/月 (2)6か月超 :273単位/月 |
| リハビリテーションマネジメント加算(ハ) | (1)6か月以内:793単位/月 (2)6か月超 :473単位/月 |
また、事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合はさらに270単位の加算が可能です。
リハビリテーションマネジメント加算について詳しくはこちらの記事で解説しています。
項目一覧に戻る
短期集中個別リハビリテーション実施加算
退院・退所後又は要介護認定日から3か月以内の利用者に対し、1週間に2日以上、1回40分以上の個別リハビリを実施する際に加算できます。算定される単位数は1日あたり110単位です。
短期集中個別リハビリテーション実施加算について詳しくはこちらの記事で解説しています
項目一覧に戻る
認知症短期集中リハビリテーション実施加算
認知症短期集中リハビリテーション実施加算は、認知症と診断され、生活機能の改善が見込まれる利用者に対して、退院(所)日または通所開始日から3か月以内にリハビリを集中的に行った場合に算定できる加算です。
| 項目 | 加算単位数 |
|---|---|
| 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) | 240単位/日(週2日を限度) |
| 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) | 1,920単位/月 |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算について詳しくはこちらの記事で解説しています
短期集中個別リハビリテーション実施加算とは? 算定要件や短期集中リハビリテーション実施加算・認知症短期集中リハビリテーション実施加算との違いについて解説項目一覧に戻る
生活行為向上リハビリテーション実施加算
作業療法士または研修を修了した理学療法士・言語聴覚士を配置し、生活行為の向上を目的としたリハビリ計画を作成・実施することを要件として加算されます。開始時と終了前にリハ会議を開き、月1回以上の居宅訪問評価を実施してPDCAを回します。なお、リハビリテーションマネジメント加算を算定していることが前提となります。必要に応じてLIFE等へデータを提出し、成果を検証します。
1か月に1,250単位を6か月以内の期間に限り算定可能です。
短期集中個別リハビリテーション実施加算・認知症短期集中リハビリテーション実施加算とは併算定できず、重複月は6か月に算入されません。
若年性認知症利用者受入加算
若年性認知症の利用者に対し、個別の担当者を配置し、利用者の状態や生活環境に応じた支援が必要です。算定される単位数は1日あたり60単位です。
項目一覧に戻る栄養アセスメント加算
管理栄養士を配置し、医師やリハビリ職、看護・介護職等と協働して利用開始時と3か月ごとに栄養アセスメントを実施、その結果をLIFEを用いて厚生労働省へ提出すると加算可能です。結果を利用者・家族へ説明し必要に応じ栄養相談をおこないます。算定単位数は1か月あたり50単位です。定員超過・人員基準欠如月は算定不可で、栄養改善加算など一部加算とは併算定できません。
項目一覧に戻る栄養改善加算
管理栄養士を配置し、低栄養または低栄養の恐れがある利用者に対して栄養改善サービスを行った場合に加算できます。算定単位数は1回あたり200単位で、3か月以内、月2回まで算定可能です。 ただし、3か月ごと栄養状態の評価において、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定できます。
項目一覧に戻る口腔・栄養スクリーニング加算
口腔・栄養スクリーニング加算は、利用者の口腔機能と栄養状態を6か月ごとに評価する加算です。様式にそって評価を実施し、結果を文書で報告などの要件があり、必要時は歯科医・管理栄養士へ連携をおこないます。1人あたり6ヵ月ごとに1回の算定が可能です。栄養アセスメント加算・栄養改善加算・口腔機能向上加算などを算定している場合は加算単位数が変わります。
| 項目 | 加算単位数 |
|---|---|
| 口腔・栄養スクリーニング加算(I) | 20単位/回(6月に1回を限度) |
| 口腔・栄養スクリーニング加算(II) | 5単位/回(6月に1回を限度) |
項目一覧に戻る
口腔機能向上加算
口腔機能向上加算は、通所リハで口腔機能低下が懸念される利用者に専門職(ST・歯科衛生士・看護職員)を配置し、個別計画に基づく口腔ケア・嚥下訓練などを行う加算です。月2回まで算定可能で、3か月ごとに再評価して継続可否を判断。。常勤換算1名以上の専門職が計画書を作成しケアマネへ共有しリハビリテーションマネジメント加算やLIFE連携の有無などで算定できる項目は変わります。
| 項目 | 加算単位数 |
|---|---|
| 口腔機能向上加算(Ⅰ) | 150単位/回(月2回を限度) |
| 口腔機能向上加算(Ⅱ)イ | 155単位/回(月2回を限度) |
| 口腔機能向上加算(Ⅱ)ロ | 160単位/回(月2回を限度) |
項目一覧に戻る
重度療養管理加算
重度療養管理加算は、喀痰吸引や中心静脈栄養など医療的ケアが必要な利用者に対し、適切なリハビリテーションと医学的管理を組み合わせることで、健康状態の維持・改善を図ることを目的とした加算です。要介護度3、4、5に該当する方が対象となります。算定単位数は1日あたり100単位です。
項目一覧に戻る中重度者ケア体制加算
人員基準上の員数に加えて、看護職員または介護職員を常勤換算で1以上確保し、過去3か月で要介護3〜5の利用者が30%以上を占めると算定できます。通所リハビリテーションを提供する時間帯に、専らリハビリテーションの提供に当たる看護職員を1名以上配置することも必要です。算定単位数は1日あたり20単位です。
項目一覧に戻る科学的介護推進体制加算(LIFE加算)
科学的介護推進体制加算(LIFE加算)は、LIFE(科学的介護情報システム)を活用し、利用者のADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況などの情報を厚生労働省へ提出し、必要に応じて通所リハビリテーション計画を見直すと算定できます。算定単位数は月あたり40単位です。
LIFE(科学的介護情報システム)について詳しくはこちらの記事で解説しています。
項目一覧に戻る
事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所リハビリテーションを行う場合
事業所と同一建物に居住する利用者、または同一建物から通う利用者に通所リハビリテーションを提供する場合に適用される減算です。該当する場合は1日あたり94単位が減算されます。ただし、利用者が傷病などの理由で移動が困難であり、送迎が必要と認められる場合には適用されません。
項目一覧に戻る送迎を行わない場合の減算について
利用者が自ら事業所へ通う場合や家族が送迎を行う場合、事業所が送迎を実施しない場合には送迎減算が適用されます。片道の場合は47単位、往復の場合は94単位が減算されます。なお、同一建物減算が適用されている場合には重複適用されません。
項目一覧に戻る退院時共同指導加算
退院時共同指導加算は以下の条件を満たすと、1回限り600単位を算定できます。
● 事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが入院施設で退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導を実施し、内容を通所リハビリテーション計画に反映させる
● カンファレンスの内容を記録する。
● 算定は1回/退院に限り可能。
移行支援加算
移行支援加算は以下の要件に該当する場合に評価対象期間の末日が属する年度の次の年度内に限り1日当たり12単位を算定できます。
● 評価対象期間において通所リハビリテーション終了者のうち、指定通所介護等を実施した者の割合が、100分の3を超過
● 評価対象期間の利用状況を平均利用月数と比較し、27%以上の割合で利用
● 評価対象期間中にリハビリテーションの提供を終了した日から起算して14日以降44日以内に、通所リハビリテーション終了者に対して、電話等により、移行情報の実施状況を確認・記録
● 通所リハビリテーション終了者が指定通所介護等の事業所へ移行するにあたり、当該利用者のリハビリテーション計画書を移行先の事業所へ提供
サービス提供体制強化加算
サービス提供体制強化加算は、通所リハの介護・看護職員など体制を評価される加算です。介護職員のうち介護福祉士の占める割合や勤続年数などで項目を選択して届出・算定をおこないます。スタッフ構成を月次で検証し、届出書と勤務表で証明することが必要です。
| 項目 | 加算単位数 |
|---|---|
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22単位/回 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18単位/回 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6単位/回 |
項目一覧に戻る
介護職員等処遇改善加算
介護職員等処遇改善加算は4段階に分かれており、それぞれの算定要件を満たすと加算率が上がる仕組みです。
| 加算区分 | 職場環境等要件 | 昇給の仕組み | 改善後賃金年額 440万円 | 経験・技能のある 介護職員の有無 サービス提供体制強化加算(Ⅰ)or(Ⅱ) | 加算率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加算Ⅰ | ◎ (13項目以上) | 〇 | 〇 | 〇 | 8.6% |
| 加算Ⅱ | ◎ (13項目以上) | 〇 | 〇 | ー | 8.3% |
| 加算Ⅲ | 〇 (7項目以上) | 〇 | ー | ー | 6.6% |
| 加算Ⅳ | 〇 (7項目以上) | ー | ー | ー | 5.3% |
項目一覧に戻る
まとめ
通所リハビリテーションの加算制度は、利用者の健康維持や生活の質向上を目的とし、多岐にわたる要件が設定されています。適切な加算を理解し、事業所のサービス向上に活かすことが重要です。自施設の人員配置や運営状況を見直し、加算要件を満たすための計画を立て、利用者に最適なケアを提供しましょう。
執筆者プロフィール
北野百恵(理学療法士/ライター)
デイサービスで介護分野のリハビリを経験したのち、急性期病院で地域医療にも貢献。3学会合同呼吸療法認定士の資格を持ち、内部疾患にも精通し、現在も病院でリハビリに従事している。医療現場での経験を活かして、読み手に適切な情報が届くライターとしても活躍。